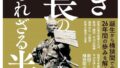信長満十六才の天文十九年1550年 その1
信長が自らの戦いを開始する意思をはっきりさせたのは、天文十九年(1550)あたりからだろう。そこでこの年前後のことからまずは検討していきたい。参考にするのは『愛知県史 通史編3 中世2・織豊』(以下県史3)で、執筆は中京大学名誉教授の村岡幹生氏だ。
信秀は天文十八年(1549)以前から重い病に臥せっていたようだ。県史3は萬松寺住職の下火語(あこのご)に「突然の病で急激に容貌が変わった」とあることから脳梗塞ではないかとしている。NHKの大河ドラマ「麒麟がくる」では小豆坂の戦いで受けた傷が原因としていたが、まだ40才前の年齢であるからには、かなり大きな病、あるいは傷・毒物等(による病変)だったのだろう。
そして信秀はこの年天文十八年に家督を信長に譲ったとされる。四月の手紙で伊勢内宮の禰宜が信秀を入道と呼び、若殿の存在を認識していたこと、また信秀が十一月二十八日に祖父江秀重あてに中島郡の代官を申し付けている手紙で弾正忠ではなく備後守を名乗っていること、信長が十一月日として熱田八ヶ村向けの制札(信長の初出文書)を出していることからだ。
ただ、信長はこのとき弾正忠を名乗っていないし(署名は藤原信長)、近年では弟の信勝と家督を半分ずつに分けたのではないか、という見方がされるようになってきている。

思うに、このころ信秀は、鎌倉街道筋を抑える古渡の城(平城)から、福谷・岩崎方面からの街道を抑える末森城(山城)へ信勝を連れて移っているから、鎌倉街道筋を初陣を済ませた信長に守らせ、末森方面の街道を病の自らと若い信勝で守る作戦だったのではないか。家臣団もそのために二手に分けたのだろう。
天文十八年(1549)十一月になると太原崇孚雪斎率いる今川勢が安城城を落とし、いよいよ信秀は、窮地に陥っていた。そんな情勢の中、年が明けて天文十九年(1550)の正月19日に犬山衆、楽田衆が蜂起した。春日井原(現在の名鉄小牧線沿い)を南下して攻め寄せてきたのだ。天文十七年と思われる信秀と斎藤道三との和睦により、美濃と国境を接する犬山の織田一族(横山住雄によれば心甫宗伝)がこの和睦を良しとしなかったのだろう。末森城より北に位置する守山城の信秀弟信光が出兵して、庄内川を越えさせることなくこれを撤退させた。

この頃信秀がすでに末森城に入っていたのかははっきりしないが、たとえ入っていたとしても、病身の信秀と若い信勝では出兵することなどできなかっただろう。信光がいてくれたことで弾正忠家は持ちこたえている。