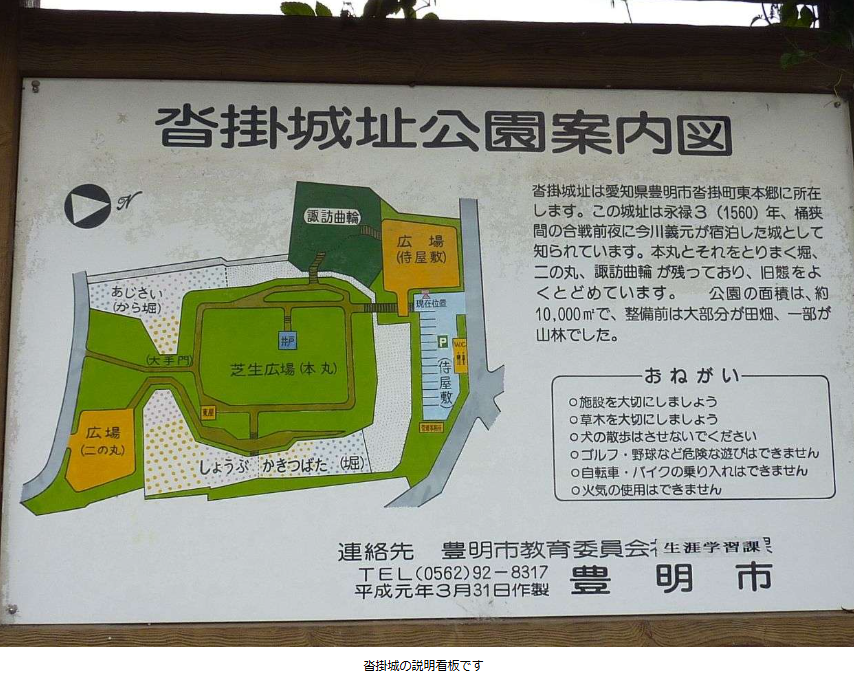※この記事を書いた当時はまだ新説に至っておらず、現在の見解とは異なっている部分があることをご了承ください。
2013年8月28日
前回ご紹介した鷲津と丸根の砦は信長の一級資料である信長公記に書かれており、その存在を疑うべくもありません。場所も現在でははっきり特定されています。しかし今回紹介する三つの砦は、信長公記には登場しておらず、その存在は謎です。
しかし二つの砦で大高城の北や東側を封鎖しておきながら、南側に何一つ砦が存在していないというのは合点がいかないところです。城を囲んで孤立させることが目的なのですから。

『張州雑志』などの史料によると、大高城の南にも3つの砦が築かれたようです。まず名古屋市緑区大高町北横峯あたりの小山に作られた正光寺砦です。大高城の南東700mで、丸根砦からは南西800mに位置し、丸根砦と連携して、二つの砦の間にある大高道を封鎖し補給を断つことが出来ました。
また大高城の南すぐ向かい側にある曹洞宗寺院春江院のあたり(緑区大高町西向山)にも向山砦を築いたとされています。ただここはあまりに城に近く、その存在はやや疑問視されています。

最後の一つは大高城の西800mの火上山砦で、名古屋高速大高インターチェンジの西側にある氷上姉子神社の元宮のある山のあたりだったようです。現在も取手山という地名が残っています。
当時北側にあった海岸線との間に道があり、海岸線からの補給を経つことができる位置でした。これらの砦によって、大高城は完全に補給を絶たれて孤立することになりました。

つまり信長の砦構築作戦によって、今川方にとって重要な尾張国内の最前線基地二つが孤立させられ、後詰(救援)を求めている状況になったのです。こうした状況に対して、今川義元が自ら大軍を率いて救援に向かった、というのが桶狭間合戦のきっかけではないかと考えられます。
よく言われているように義元が上洛を目指したとか、尾張を攻め取ろうとしたとかではなく、あくまで救援と拠点確保が目的で、うまくいけばその後でさらなる尾張侵攻も可能と考えていた、という事ではないかと考えます。
この時までに信長が尾張全体を掌握し、それなりの力をつけていることは義元も十分承知しているはずですから、そんな信長に絶対的に勝利するため大軍を率いてきたことは、しごく当然のことでしょう。
信長にしてもこうして敵の城を囲めば、今川方が何らかの敵対行動に出てくることは計算の上でしょう。したがってそれに対する作戦は考えられていたことと思われます。ただ義元本人が出陣してくることまで予想していたかは疑問が残りますが。
ということでいよいよ次回は桶狭間合戦時の、信長と義元の動きを追ってみたいと思います。