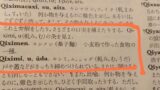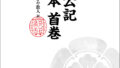先日、25年6月21、22日と伊勢に行ってきました。その詳細はいずれ書きたいとは思っていますが、なにせすごい情報量なので、整理して信長の時代に絞り込めたら、また書こうと思います。今回はフィスブックにも書いた、伊勢うどんと棊子麺の話をこちらにも再掲しておきます。

先日の伊勢行きでまず食べたのが伊勢うどん。伊勢市駅の北にある「まめや」という店でミニ天丼セット1450円を。美味かった。好きではない麺ですが、汁(というよりタレ)は飲み干してしまいました。聞けばムロ出汁のたまり汁のよう。つまりはきしめんと同じで、出汁で伸ばせばきしめんの汁になるかも。そこで伊勢での宴会ネタとなった「伊勢うどんときしめんの関係について」のお話です。
そもそもきしめんはあの山科言継が1570年に食べていたくらいで、1603年から翌年にかけてイエズス会から出版された『日葡辞書』にも「Qiximen」という項目があるほどの当時メジャーな食べ物でした。(「Qiximen.キシメン(棊子麺) 小麦粉で作った食べ物の一種.」)。今のきしめんのような麺料理ではなく、薄く伸ばした小麦粉をこねて茹で、きな粉(と塩、あるいは醤)をかけた酒の肴でした。信長もきっと食べていたはず。その後江戸時代に入ってもうどんとは別に「棊子麺」という料理があったようですが、どうやらだんだん廃れてしまったようです。
ところが1810年に伊勢・河崎に「きしめん屋」の屋号を持つ大西由兵衛なる人物が登場。その後1843年に犬山市中本町で「きしめん 是迄十六文うり この代十四文二引下ケ」と書かれた記録もあります。河崎のきしめんがどういうものかはわかりませんが、犬山のものはなんとなく現代のきしめんのような汁物麺を想像させます。つまりこの頃、今のきしめんのような商品が伊勢や犬山にはあったと思われるわけですが、なぜか名古屋には文献がない。
きしめんは名古屋のものだと考える原理主義者としてましては、ここで大胆に想像してみます。そもそも江戸時代の始めには名古屋はうどんが名物でした。そこで1700年代中頃に、ある人がうどんではない名物を作ってやろうと、刈谷にあった芋川うどん(平たい麺のうどん)を模倣して(要はパクって)、かつてあった棊子麺という言葉をパクって「名古屋名物きしめん」と命名して売り出したのではないか、と。これが大ヒットし、たぶん伊勢参り途中の熱田宿の客などにもウケて、それが1800年代に伊勢や犬山に店ができるほどポピュラーな食べ物となった、ように思います。
このきしめんは伊勢にはずっと残っていて(今でも出す麺類食堂はあるそうですし、宴会のときに「90過ぎの古老が昔は伊勢うどんなどなくて、きしめんを食べていた」と話していたことも聞きました)、伊勢うどんが名物となる前は普通に食べられていたのではないかと思います。じゃあ伊勢うどんは何なんだ、という話ですが、これは考察があったら教えてもらいたいものです。
私が思うには、戦後にゆでめんが市場などで売られるようになった時、買ってきて自宅で食べる頃には伸びてしまって、伊勢うどん状態になってしまっており、それが家庭で食べるうどんの普通の状態になったのでしょう。家庭の味はやがてソウルフード化し、目ざとい人がそれを観光名物化したのではないでしょうか。
まあ「しらんけど」ですけど、ぜひどなたか、伊勢うどんに関してお説を教えていただきたいと思います。ただ、名古屋のきしめんもいまだに「築城時に振る舞われた」「紀州から来た紀州麺だ」「雉肉が入ったきじ麺だ」などと曰われる人が多いので、伊勢うどんもぜひ本当のところが知りたいものです。ちなみにきしめんは打つのが大変な麺で、手軽に打つ・短時間で茹でるための形状ではありません。伊勢うどんの製法も知りたいなあ。地元の人はあんまり食べないというのも本当でしょうか。
以下の私のブログ(昔、中日新聞Webで書いたものの転載)に詳細は書いています。
刈谷の芋川うどんについてはこちら