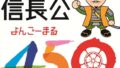2016年8月20日

1565年の堂洞合戦の後、信長は金山(岐阜県可児市兼山・1656年に兼山と改名)まで攻略したようです。ただ良好な資料がなく、『信長公記』にもありませんのでよくわかりません。
のちに様々な軍記ものに書かれたことなどから想像するしかありませんが、江戸中期1792年に書かれた『金山記全集大成』というものが金山にはあり、それによれば、堂洞合戦の加治田城佐藤紀伊守が4キロほど西にある関城の長井隼人を攻め、その際に森三左衛門尉可成が信長から援軍として差し向けられた、とのこと。

そこでの勝利の後、そのころ鳥峰城(うほうじょう)と呼ばれていた金山城が森可成に与えられたとされています。まあ、だいたいはそういうことかと。三男森蘭丸は1565年の生まれですから、この城が誕生の地かもしれません。加治田城からは東に10キロほどの、木曽川を越えたところです。
鳥峰城を森可成は金山城とし、ここを拠点にこの地方の久々利城、土田城、大森城などの国人を織田の味方につけていったようです。ちなみに関城というものが本当にあったかについては、最近ちょっと疑問視されています。

森可成は源氏の出身とされ、尾張国葉栗郡蓮台(現在の岐阜県羽島郡笠松町田代)の人。もともとは美濃守護土岐氏に使えていたようですが、可成の父の代から織田信秀に、やがて信長に仕えるようになりました。最後の守護土岐頼芸を追い出した斎藤道三とは合わなかったのかもしれません。
可成は信長より10歳ほど年上で、信長公記では道三救援の撤退戦や稲生の戦いでも名前が登場し、若き信長を支えた側近だったようです。有名な森蘭丸の父親でもあり、森家は江戸時代も続きますから、それゆえ「出自は源氏」という系譜も残っているのでしょう。

さてそんな金山城ですが、ここもよく遺構が残っています。標高276mの本丸の礎石跡、主郭の石垣、枡形虎口など、さらに下段の眺望の良い曲輪、東側の大堀切など、2万平方メートルという広大な縄張りが、見学しやすいように整備されています。
しかもクルマで上がれるので、手軽に山城が楽しめます。夏でも大丈夫ですからお出かけください。東海環状自動車道可児御嵩インターから10分ほどです。

勇猛で知られた森可成は多くの子を成しますが、5年後の1570年には戦死、嫡男可隆も同年に戦死、さらに信長の小姓となっていた蘭丸、力丸、坊丸は1582年の本能寺で戦死、金山城を継いでいた次男の森長可は1584年の小牧・長久手の戦いで戦死。最後に残った六男忠政が1600年までこの城におり、現在の遺構はこの頃のものとされています。

忠政が転封されたあと、城は解体され破城されました。ところが天守の解体資材は、下を流れる木曽川を使って下流の犬山城まで運ばれ、現在の国宝犬山城となりました。これは今から55年前の解体調査で一旦否定されていますが、それでも多くの人がその後も調査を続けて、両天守台の測量による形の一致や、犬山城の天守台石積みが江戸前期の手法であることなどで、事実であるとしています。このあたりの話は、金山歴史民俗資料館(岐阜県可児市兼山674-1)でご確認ください。森氏の前にこの城を作った斎藤正義からの歴史もしっかり学べますよ。