2016年9月14日
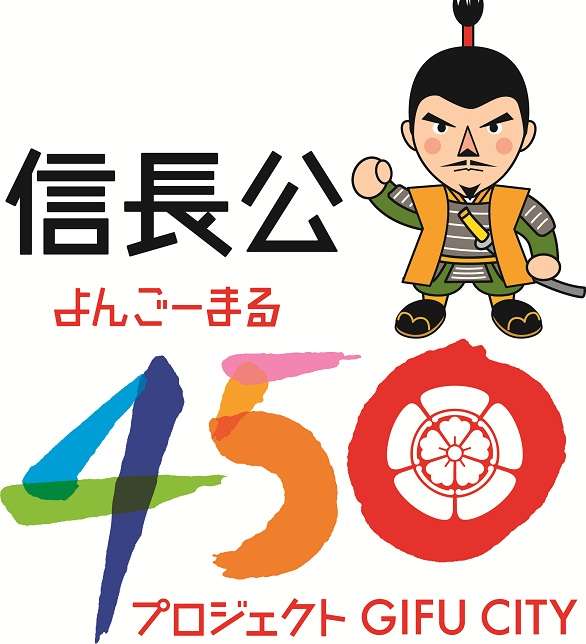
この連載で書いてきた桶狭間の戦い以降、信長の美濃攻めのお話ですが、いよいよ稲葉山城(後の岐阜城)を攻略する直前まで来ています。
それは1567年のことで来年2017年は450年目となり、岐阜市ではいろいろと企画が考えられているようです。それが「2017年織田信長公岐阜入城・岐阜命名450年」岐阜市信長公よんごーまるプロジェクトです。詳細はこちらからどうぞ。
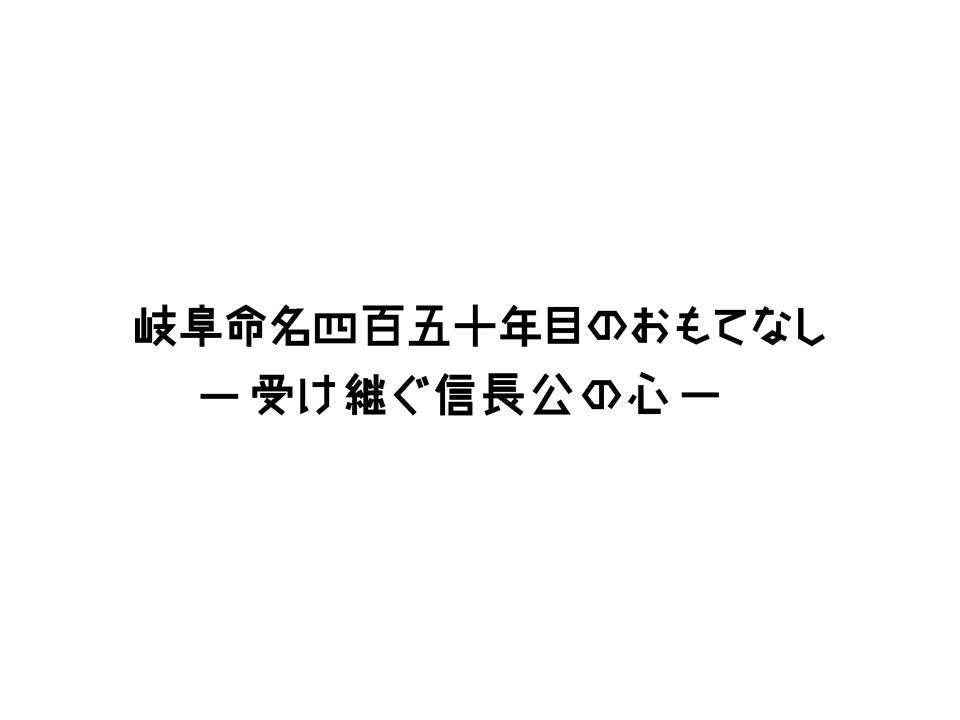
よんごーまるプロジェクトのサイトにも信長年表がありますが、桶狭間以降の7年間はわずか3項目しかありません。しかも1566年のところには、墨俣城を築城して龍興を破ると…。信長がその後岐阜に在住したのは9年間、安土は5年間ですから、桶狭間以降の7年はもうちょっと注目されてもいいと思います。
ということで、今回はこの間の動きを年表にしてわかりやすくしてみました。ただ、とにかくこの間は資料も少なくわからないことだらけです。そこで、この頃の信長や斎藤氏の研究者として日本の第一人者である、岐阜県在住の横山住雄先生の説を主に参考にさせていただきました。
■■1560年(永禄3年) 信長満26歳■■
5月以前 犬山城織田信清、離反か
5月19日 桶狭間の戦い
5月23日 松平元康(のちの徳川家康)、岡崎城へ入る
6月2日 信長、西美濃・安八郡へ侵攻
6月ごろ 斎藤義龍、南近江六角氏と手を結ぶ
8月 松平元康と水野信元、石ケ瀬(大府市)の戦い
8月23日 信長、再び美濃侵攻か
12月 義龍、近江の伊吹へ侵入
※信長は桶狭間勝利の勢いで、義理父の敵でもある斎藤義龍を攻めるため、西濃地方へ侵攻しますが、義龍は強く勝利は得られません。義龍は幕府中枢へ入ろうと六角氏と組み、北近江の浅井氏と戦い始めます。信長はその浅井氏と手を結ぼうと画策を始めます。
■■1561年(永禄4年) 信長満27歳■■
2月ごろ 信長、信元仲介で元康と同盟か(4月説も有り)
2月 義龍、左京太夫となり一色へ改姓
4月ごろ 義龍、近江へ侵攻
4月上旬 斯波義銀と吉良義昭、上野原の会見
4月11日 元康、東三河牛久保城攻め
4月上旬 信長、高橋郡(豊田市)侵攻、梅ガ坪城、伊保城、八草城攻め
5月ごろ 信長、挙母城(豊田市)の中条氏を滅ぼし高橋郡は尾張編入
5月ごろ 信長、浅井氏と同盟し、賢政が長政に改名か
5月11日 義龍急死(33歳)、後継は龍興(15歳か)
5月14日 信長、美濃侵攻・森部の戦いで信長大勝
5月23日 軽海十四条の戦い、のち一時撤退
6月中旬 信長、安八郡神戸(神戸町)まで侵攻か
6月ごろ 龍興が長井隼人を筆頭家老として迎え入れたか
6月16日 武田信玄が出兵準備したが信長撤退で取り止めと長井隼人へ手紙
6月 信長、敵対する犬山方の於久地城(大口町)攻撃(永禄5年説も有り)
8月 信長、尾張守護斯波義銀と石橋義忠と共に追放か
8月 西美濃大垣城が信長方へついたか
9月 元康、東条城(西尾市)攻め
※この年前半に松平元康と同盟を組み、高橋郡を尾張に編入して、東側の守りを堅めます。そして1554年頃といわれている守護の会見が、横山先生はこの頃行われたとされます。5月には一色姓を得て飛ぶ鳥を落とす勢いだった義龍が急死し、信長に大チャンスが訪れます。一気に美濃へ侵攻して西濃地方を手に入れたかに見えますが、犬山の織田信清の謀反のためか、撤退することになります。このあたりは今一つよくわからないところです。
■■1562年(永禄5年) 信長満28歳■■
2月頃 信長、龍興と和議か。以降二年は平和に
2月4日 元康、上之郷城(蒲郡市)攻略 妻子奪還
※撤退後、義龍との和議を結び、この年はほとんど何もありません。翌年の小牧山城築城計画を練り、守護を追放したあとの「信長の国・尾張」を安定させるため内政に手をつくしていた、と考えたいところです。しかし犬山の勢力は尾張の丹羽郡、葉栗郡あたりを奪っており、海西郡や長島のあたりは一向宗にかなり奪われていました。一方、松平元康は着々と三河を手中に収めつつありました。
■■1563年(永禄6年) 信長満29歳■■
2月 信長、小牧山鍬入れ(起工)
3月2日 信長娘五徳と松平信康婚約か
6月ごろ 松平元康が徳川家康に改名
6月ごろ 信長、上総介から三介に名乗りを変える
7月 小牧山城竣工、清須から移転
秋 三河一向一揆勃発
数え30歳となって、いよいよ信長の理想の城、安土城にも匹敵するシンボルの小牧山城と、理想都市である城下町が作られます。これによって、国の内外に安定した力を見せつけ、名乗りも変えて、ここを拠点としての上洛構想を考え始めていたのではないでしょうか。この時期に新加納の戦いなどの美濃攻めをした話がよく言われていますが、どうもそれらしい証拠は見当たりません。
ということで1564年以降は次回に続きます。

