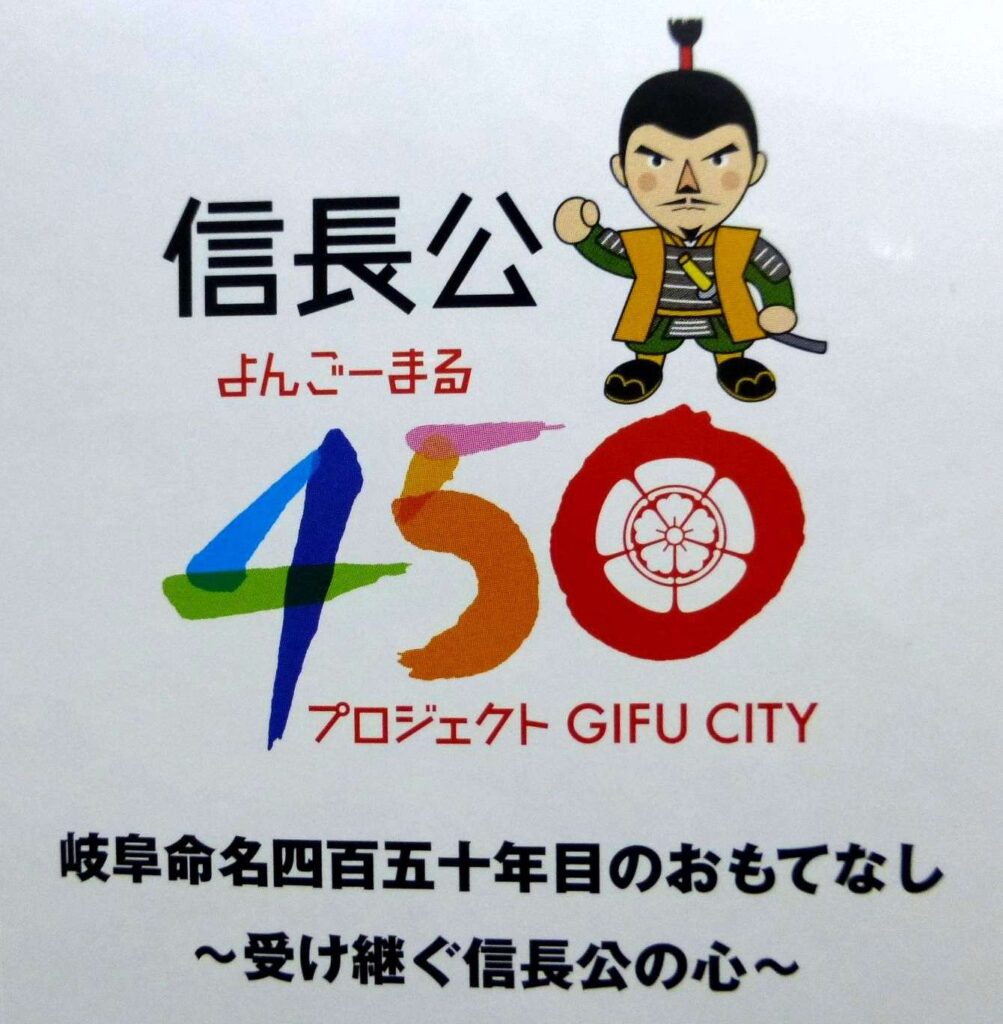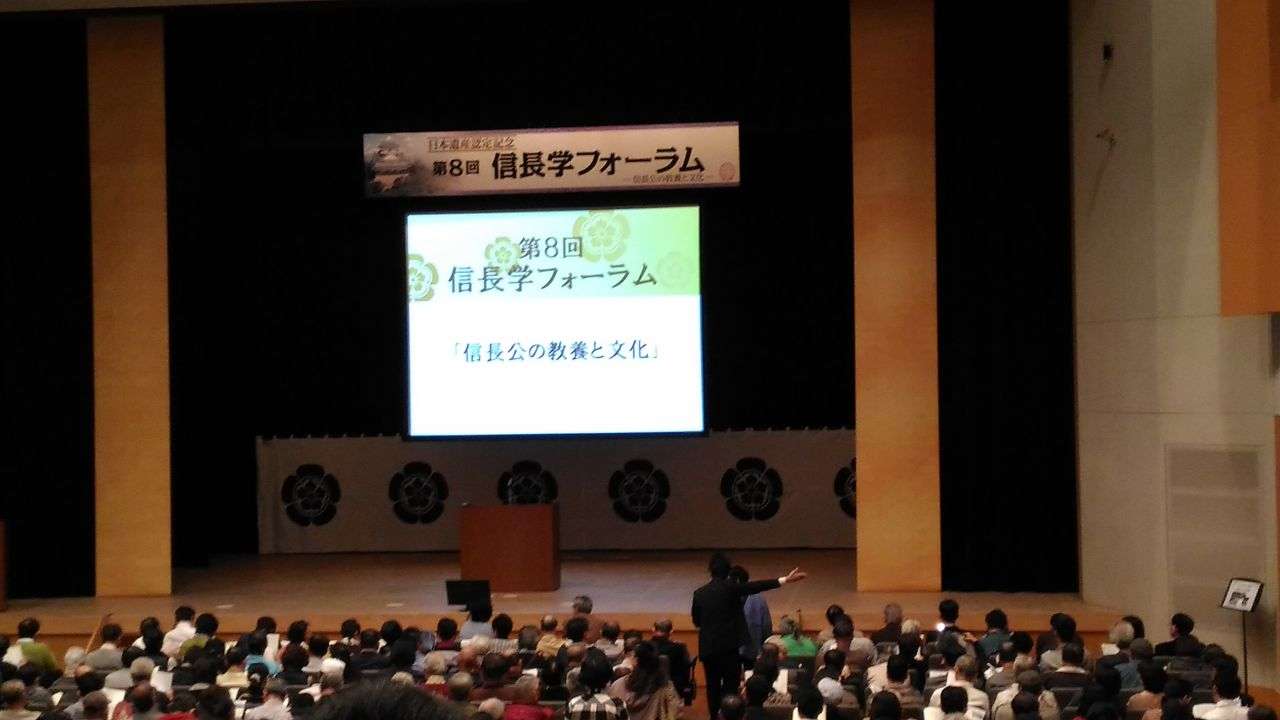2015年11月27日
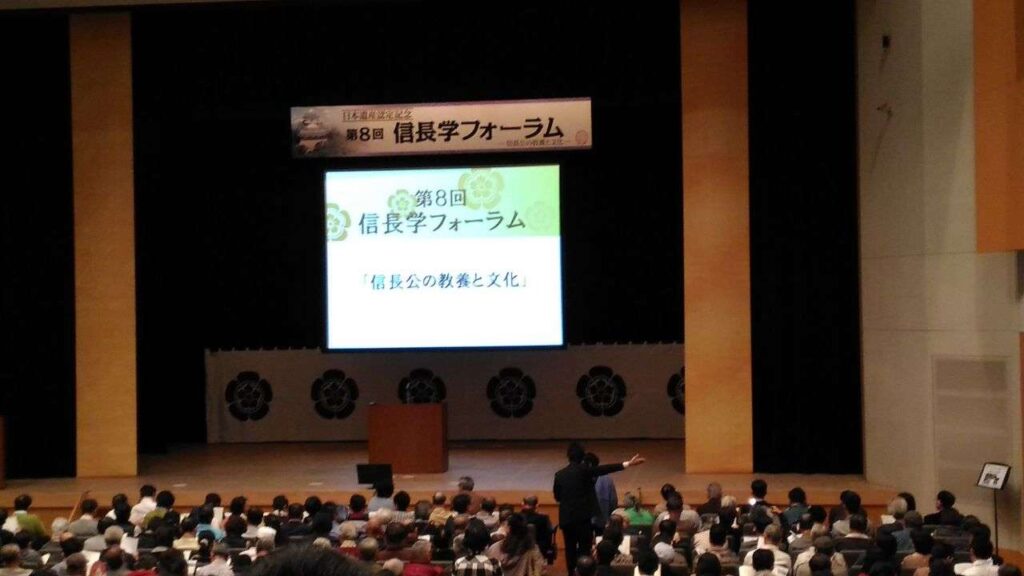
去る11月22日、「信長公のおもてなしが息づく戦国城下町・岐阜」として文化庁から日本遺産(Japan Heritage)に選定された岐阜市で、第8回の信長学フォーラムが行われました。1567年に稲葉山城(後の岐阜城)を落として岐阜城に拠点を移した信長は、その麓に巨大庭園を持つ迎賓館とも呼ぶべき館を作りました。
そこへポルトガルの宣教師フロイスらが訪れてもてなされ、記録を残したことで、世界に通じる戦国遺産として、今回日本遺産に認定されたようです。

信長が岐阜にいたのは10年間ですが、生まれてから30年以上は尾張にいました。しかし岐阜に入ってからの動きが天下統一戦であったため、昨今、信長=岐阜というイメージが強くなってきているようです。駅前には金の銅像もありますし。
2年後の2017年は、信長が岐阜に入って450年というメモリアルなので、様々な岐阜市のプロジェクトが動き出しています。信長の伝記『信長公記』も岐阜入りしてからが充実しており、尾張時代に関する首巻と呼ばれる部分は、後で付け加えられたものです。
私のような尾張の人間としてはこれらの動きはちょっと残念な気持ちもありますが、まあこれを機に自治体の枠を超えて、若き信長がもっとクローズアップされてもらいたいものです。

さて「信長公の教養と文化」をテーマとした今回のフォーラムでは、細江岐阜市長による挨拶と報告の後、東京大学資料編纂所准教授で、信長や信長公記に関する著作も多い金子拓氏が「信長と朝廷」という演題で基調講演を行いました。
天正元年の天皇に譲位をさせようという問題(結局なされず)と、信長が官位を返上した問題、京都をどう整備しようとしたのか(自身の居住所をなぜ作らなかったのか)という、それぞれが絡みあった3つの問題を資料を元に再考察してみたという内容でした。
従来、信長は朝廷と対立したとか、朝廷を意のままにしようとしたとかと言われてきましたが、資料を読むかぎりそんな意図はないように思えるという話でした。
譲位は準備している中、様々な戦いが続いて落ち着かなかったため出来なかった、官位はいったん返上して戦いに全力を注ごうとした、京都は整備途中で本能寺の変で倒れることになった、というごく当たり前とも言える結論でしたが、残っている資料を深く研究するのであればそうなるのも仕方ないのかもしれません。
ただそれがこれまでの通説を否定した結果だとすると、ちょっと物足りない気もしてしまいますね。
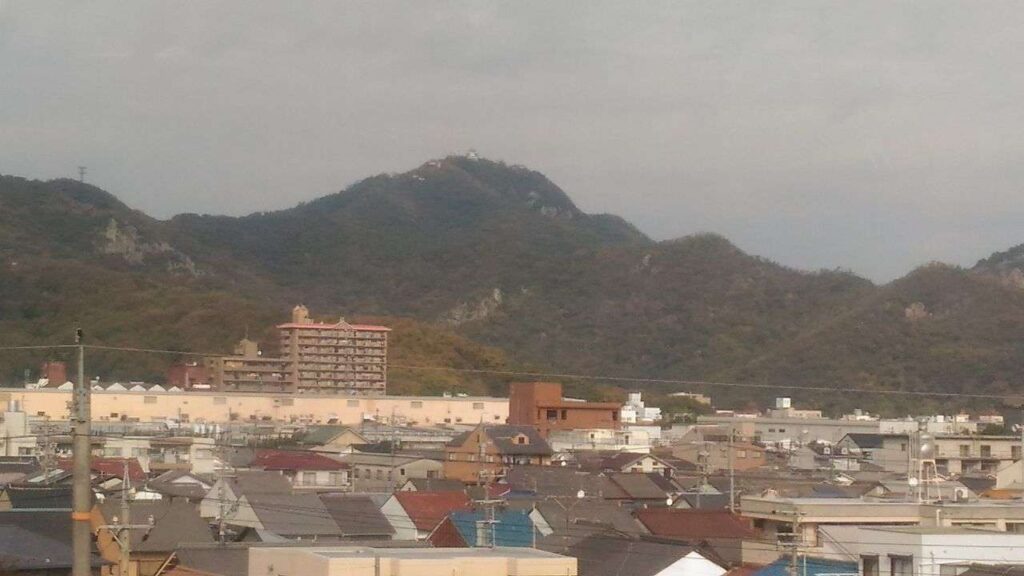
かつて戦国武将は皆天下統一を目指していたと言われていましたが、これを否定する見方が現在では主流となっています。本能寺の変は朝廷黒幕説があるほどですが、信長は朝廷と対立していたのではなく、融和を図っていた、そして朝廷を信長が支えようとしていたという説が、今後は主流となっていくのでしょう。
戦国期の研究は現在急速に進み、長年常識だったことがひっくり返りつつありますが(特に肖像画では有名な武田信玄像なども今では否定されています)、それがおもしろい反面、なんだか夢がなくなってきてしまっているようにも思えます。
この講演の後は東京大学史料編纂所教授の本郷和人氏とNHKアナウンサーの井上二郎氏による、歴史番組「知恵泉」で取材された岐阜城発掘調査の話と信長のもてなしに関しての話が、番組のVTRを見ながら行われ、比較的硬めだった金子氏の話と違って、満員の会場が大いに盛り上がりました。
最後となった出演者によるパネルディスカッションでは、細江岐阜市長が力を込める450年プロジェクトの、キャッチフレーズとロゴマークが発表されました。それは以下の写真の通りです。