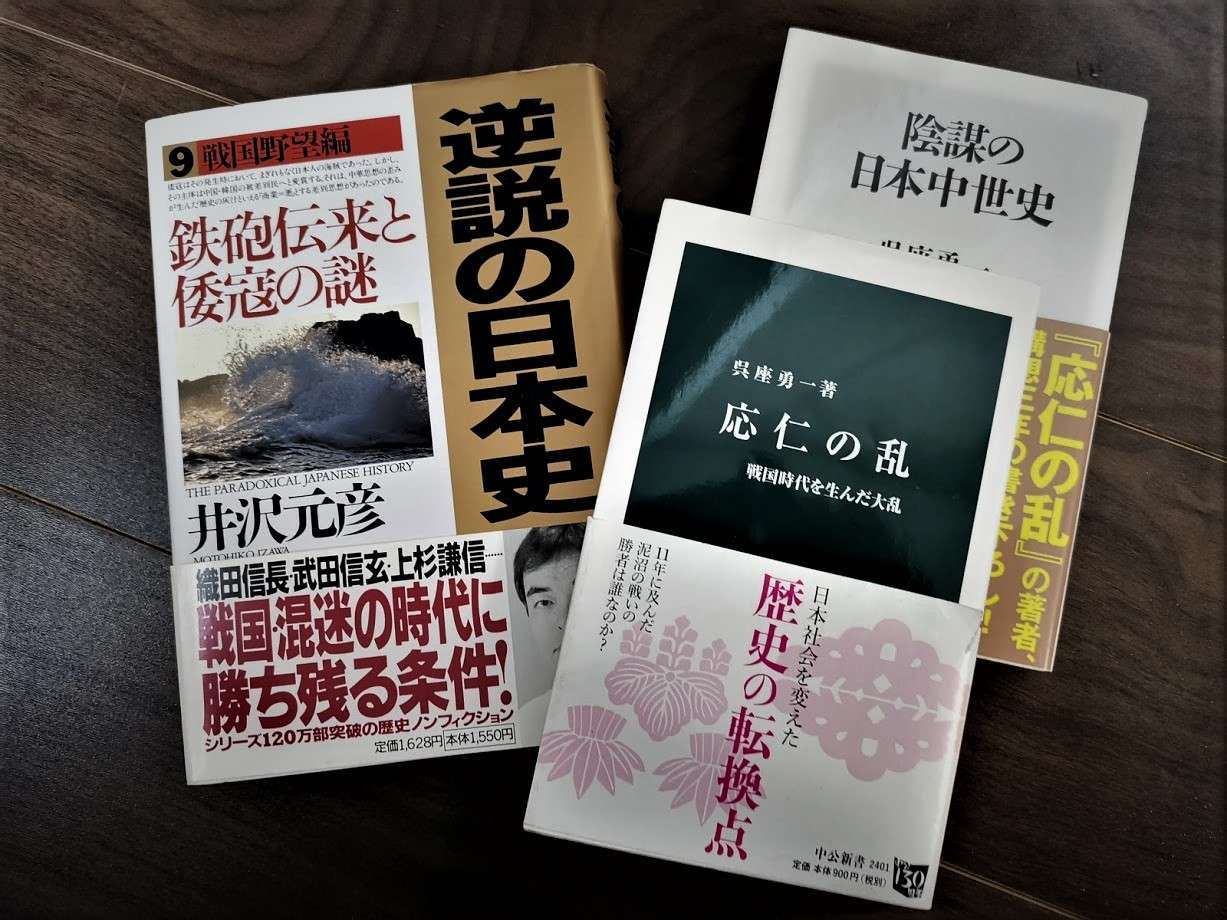2019年5月25日
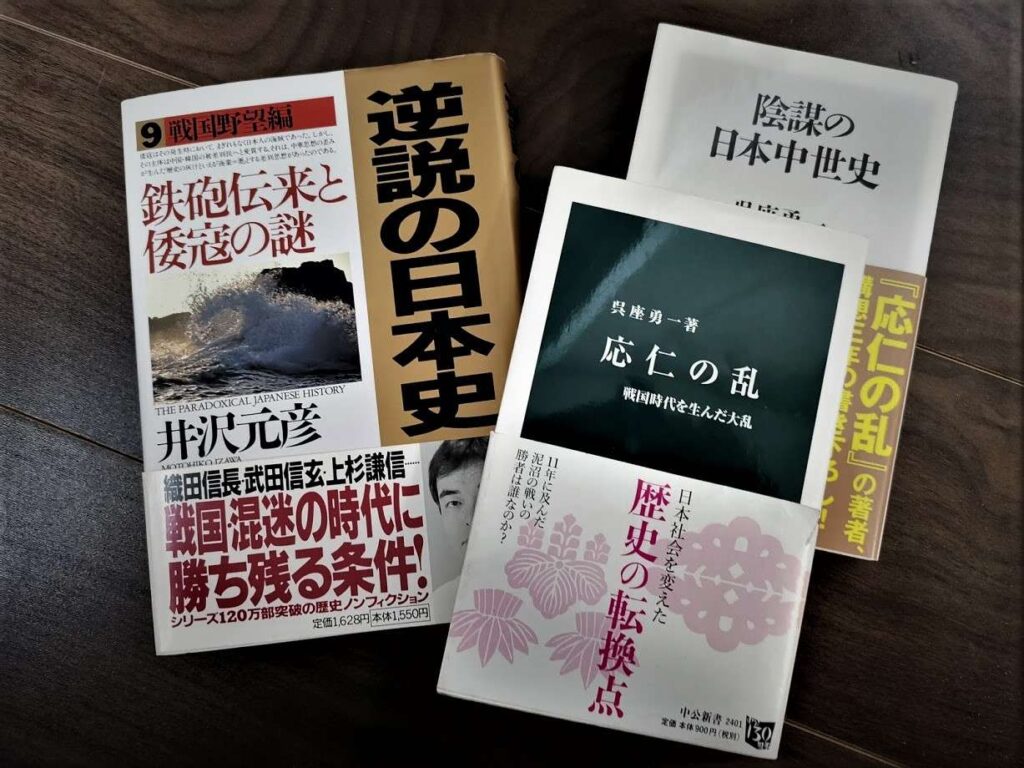
このところ、歴史作家の井沢元彦氏と歴史学者の呉座勇一氏の論争(週刊ポスト掲載)が話題になっています。
といっても歴史好きでない人にはまったく知られていないかもしれませんが。ざっくりいえば独自の日本通史を展開している井沢元彦氏の「逆説の日本史シリーズ(累計500万部以上)」に対して、「応仁の乱(20万部以上)」というベストセラー新書を持つ実証的歴史研究者の呉座勇一氏(国際日本文化研究センター助教)が、それは学問的には正しくないとして、論争になっているわけです。
井沢さんは作家らしく想像力に訴えかける面白い通史を書いていますから、読んだ人は皆、かなり影響うけるようです。司馬遼太郎の歴史小説を史実のように思っている人が多いですが、そんな感じともいえるでしょうか。対して学者による歴史研究はかなり地味な世界で、史料に対して検討に検討を重ねてそれを評価し、そうしてわかったこと以外は推論を廃し、わからないことはわからないとします。それゆえ、一般の人には面白いとはいえなくなることが多く、それなりに勉強しないと理解すら難しいことも。呉座さんの本で、なぜか爆発的に売れた「応仁の乱」は、そのあたりの勉強がまったく足らない私など、とても面白く読めたとはいえませんでした。
しかし学問という意味では呉座さんのいうことは至極もっともで、多くの研究者は当然支持していますし、もちろん私もこの論争、呉座さんの方が有利だと思います。作家である井沢さんも相当な勉強のうえ、大胆に推論を重ねていった結果、面白い歴史の流れを提示しますからあれほど売れるわけです。ただ御本人はそれが正しい歴史だと断定してしまうのでちょっと話が難しくなってしまうわけですが。またベストセラーとなっている某日本史の本など、私的に詳しい時代のあたりを読んでみると、あんまり勉強しているようには思えないので、これはちょっとどうにもダメですね。
ただ、歴史を楽しむという点では、様々な評価がなされた研究結果を横に繋いでいって、推論を導き出してみることが一番の面白さではないでしょうか。一般に学者は、エビデンスに基づき「こういう事実とこういう事実があるが、これがどう結びついているかは証明できないからわからない」とします。それはそうでしょうけど、そこをいろいろ考えるのが歴史の楽しさではないかと。ウソはいけませんが、最新の学説をもとに、歴史の流れを面白く推論していくことは、歴史を楽しむ上で重要なことではないでしょうか。
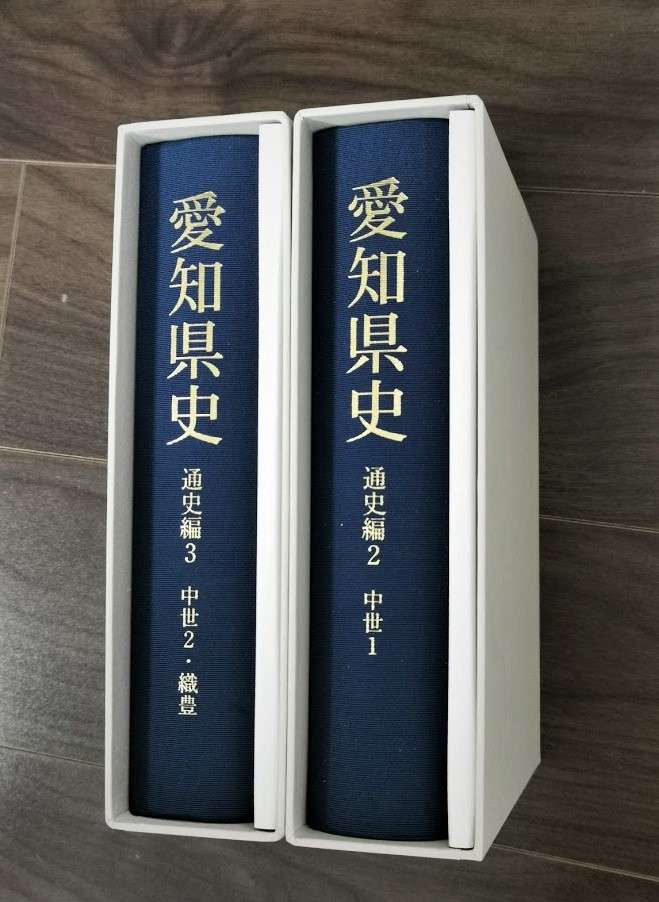
学者の方も、実証的な研究成果にもとづいてそれまでの通説をくつがえす作業をすることは重要な仕事ではないでしょうか。わからない、ではなくこう考えられるのではないかと提示してもらわないことには、歴史の通説は更新されません。その点、昨年出版された愛知県史通史編3は公の出版物ですが、信長の父、信秀時代に関しては大胆すぎるほどの説が掲載されています。以前紹介したと思いますが、信秀は今川義元と打ち合わせて矢作川以西の三河を占領し、約束を違えて岡崎まで攻め取ったので、竹千代(後の家康)が人質に出された、という話など、下手な小説以上に面白いと思います。これは中京大学の村岡先生が書かれています。
そんな県史を読んで私はさらに、信秀の義理の兄弟とされる松平本家に近い松平信定(尾張守山の領主でもあった)や、家康の叔父である水野信元らがみな名前に「信」を使っていることから、その時代の情勢の重要な鍵がそこに有るように思ったりしています。これなど何も資料などないので「わからない」とはなりますが、それで済ますというのでは、いかにも残念な気がします。このあたりは先日大須万松寺で講演させて頂く機会があったおり、すこし話をさせていただきました。

井沢・呉座論争をきっかけに最近、歴史学者・研究者のツイッターを見るようになりましたが、そこから研究者が経済的には相当に厳しい実情が見えてきました。博士号を取得してもいわゆるオーバードクターということで、大学や研究機関に常勤採用されることは厳しく、著書も多いある研究者は40歳過ぎまで、親の仕送りと、歴史研究とは全く関係ない肉体系のアルバイトで研究を続けてきたとのこと。貧困ポスドク(ポストドクター=博士号取得後、常勤研究職についていない人)などという言葉もあり、40歳を過ぎても非常勤講師などをしながら細々と研究を続けている人も多いようです。
また先日は幻冬舎の見城社長が、ある小説の印刷部数をツイートして問題になりましたが、本の売れないご時世ゆえ、どれだけ本を書いてもなかなかお金にはならないという現状が再確認されました。例えば、1000円の新書本の印税が100円だとして、これが一万部売れても著者には100万円しか入ってきません。一冊書くのに3ヶ月かかったとして、月収は30万円ほどしかありません。年間4冊、一万冊売れる本を出すなどというとても無理と思えることをしたとしても、年収は400万円。合間に講演をやっても一回あたりは数万円ですし、経験からいって準備に1日や2日はかかりますから、これも金銭的に割に合うとは思えません。研究者が本を書いて講演をしてというアクティブな活動しても、お金はついてこないのが現実なのです。
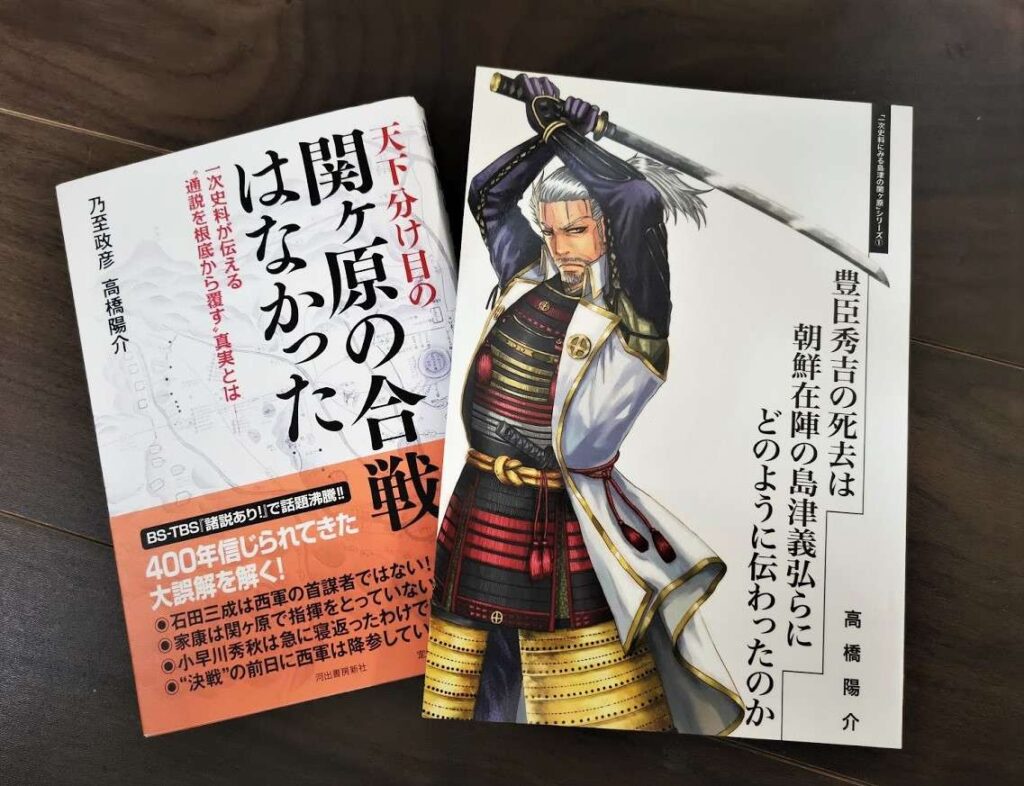
そこで思い出すのが岐阜県在住の研究者である横山住雄先生(昭和20年生まれ)。この方は、博士号を持つ研究者ではありませんが、行政書士をしながら研究を続けられ、多数の自著の自費出版も行って、尾張・美濃の中世史研究の先駆者となられました。これがどれだけ困難なことだったかは、業界は違いますが、名古屋で出版社を作って雑誌や本を出版してきた私としては実感できます。しかしそれでも今も自費出版で研究成果を発表している研究者はいます。それは「天下分け目の関ヶ原の合戦はなかった」という本で注目を集めている若手歴史研究者の高橋陽介氏(浜松在住)。栄中日文化センターで同名の講座も行われていますが、他に「一次史料に見る島津の関ヶ原シリーズ」として最近も2冊自費出版されています。
こういう人の活躍を見ると、最近目にする「ポスドクは他の仕事をしながら在野の研究者になれば」という意見に賛成しそうになりますが、ビジネス感覚のあまりない研究者志向の人がそれを実践するのは、そうとう難しいことだと思います。在野の研究者に誰もがなれるとはとても思えません。地味で仔細な分野の研究だけでは生活できない現実。何か手を考えないと、歴史研究は進まなくなってしまいそうにも思えます。どうしたらいいのか、私にはわかりませんが、そんな状況であることを、ここに少し記しておきたいと思います。文系の研究に力を入れようとしない国や自治体には期待できませんので、誰かお金持ちの歴史好きがポンと寄付をして研究機関を作ったりしてくれないものでしょうか。