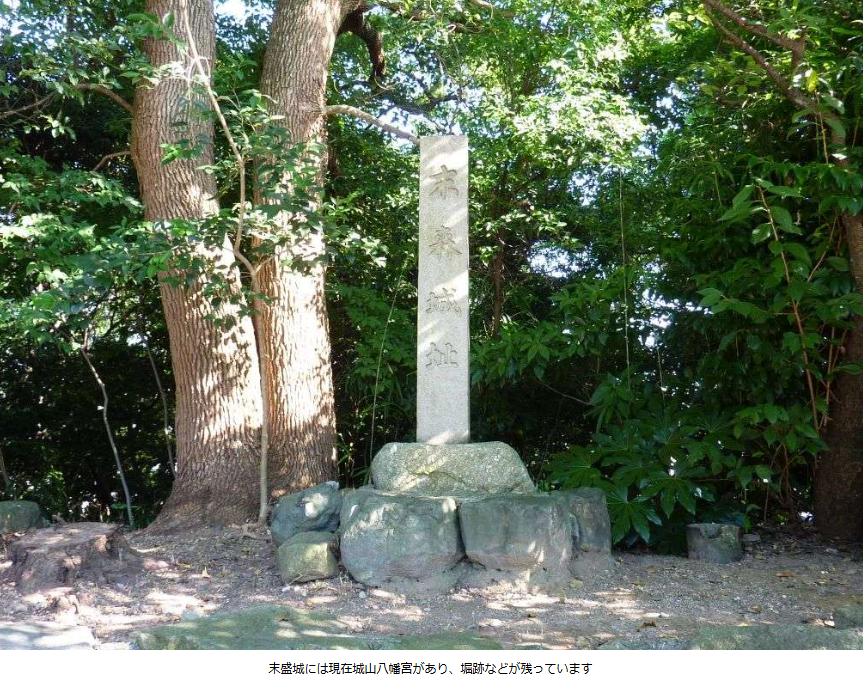2013年3月28日
1556年、信長は満22歳です。斎藤道三の死後、家中に不穏な動きが出てきています。先回書いたように、清須城の信長に対し、庄内川から東の地域がほぼ反信長となってきていました。
その勢力の中心は、信長の一番家老で那古野城を与えられていた林秀貞とその弟である林美作守、そして下社城の柴田勝家です。この三人が結託して謀反を起こし、信長を廃して弟信勝を立てることを決めていました。
そんな謀反の噂が出ている5月、信長とこの時はまだ殺されていなかった守山城主の信時の二人は、何を思ったか連れ立って林秀貞に会いに那古屋城を訪れます。林美作守はこの時「絶好の機会だから今、殺してしまおう」と秀貞にいいましたが、さすがに「三代にわたって恩を受けた主君をここで殺せない」と秀貞は信長をそのまま返しました。
この時信長が殺されていれば歴史は大きく変わったでしょう。また秀貞はこの時信長を生かしたことで、その後も家臣団にとどまれたのではないかとも思います。それでもその後24年もたってから、秀貞は結局追放されてしまうのですが。
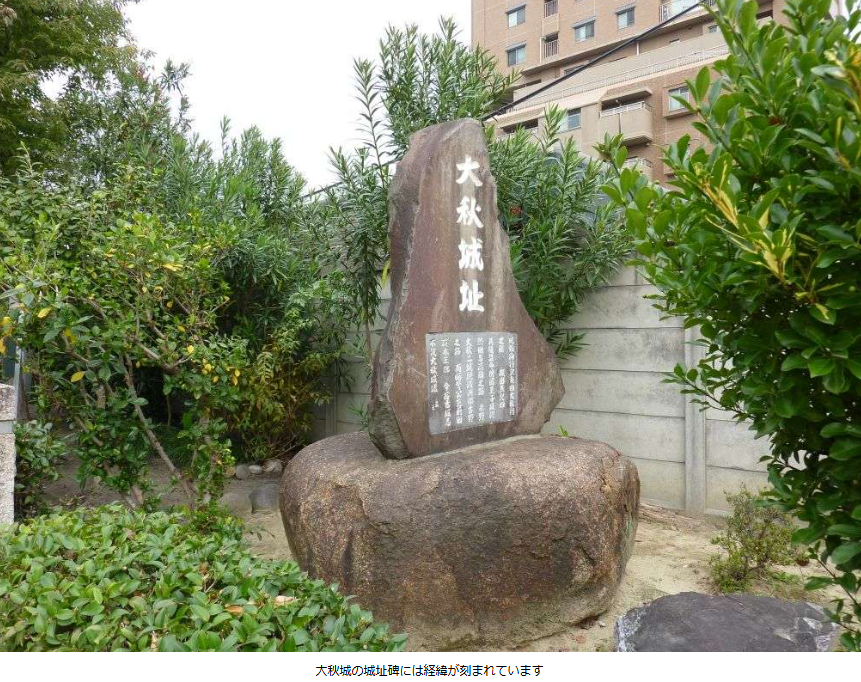
林兄弟と柴田勝家は、それから数日後に反信長を鮮明にします。中川区にあった荒子城(城址は荒子町大和ケ池、天満天神社)の前田利昌、中村区にあった大秋城(城址は大秋町2-87、大秋八幡社)の大秋十郎左衛門、同じく中村区にあった米野城(城址と思われるのは下米野町2、長松寺)の中川弥兵衛が同調し、今の名古屋市中村区、中川区、中区あたり、庄内川から東、さらに海岸に至るまでが反信長エリアとなって、清須と熱田の間を遮断しました。
荒子城は前田利家の生まれた城として有名ですが、若き前田利家と信長は男色関係であったようで、この頃は信長に使えていましたから(現在では利家は前田城の生まれとされ、信長との男色関係もなかったとされる)、利家は実家が信長に反旗を翻したことを苦悩したのではないでしょうか。また大秋十郎左衛門はかつて那古野城主だった今川氏豊の元家臣で、当時は秀貞与力となっていました。中川弥兵衛も秀貞与力です(現在では那古野今川氏に関する研究が急速に進んでいる)。

信勝側は信長の領地だった春日井の篠木三郷を奪い、これに対して信長も敵方の庄内川東側、名塚に砦(砦跡は名古屋市西区名塚町4-70、白山神社)を築きます。そこへはかつては信勝の家老であった佐久間大学盛重が入りました(現在では名塚砦は白山神社ではなく、現在の庄内川の北側にあったと考えられている)。
信長の家老が敵となり、信勝の家老が見方になるという複雑な関係です。盛重はこの時点でどうやら信長側についたようですが、最前線を守らされています。盛重は桶狭間の戦いでも前線の丸根砦を守ることになるのですが、結局信長に見殺しにされてしまいます。今ひとつ、信長に信頼されていなかったため、最前線を守ることで忠誠を示そうとしたのでしょうか。
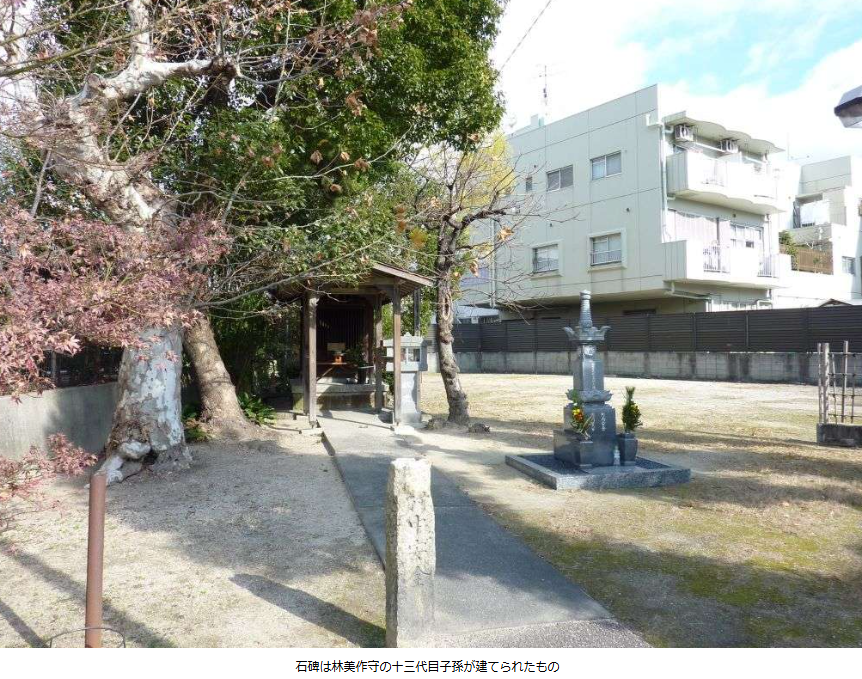
8月23日に柴田勝家勢1000、林美作勢700が出陣し、それに呼応して翌24日に信長も700弱の手勢を率いて庄内川を渡って稲生の村外れに陣取りました。やがて勝家が南東(北区中丸町のあたり?)から、林美作が南(西区香呑町のあたり?)から進んできたので、信長はまず勝家勢に攻撃を開始しましたが劣勢に陥ります。
その時信長が大音声を発して威嚇したため、敵は恐れをなし、見方は力を得て、ついに柴田勢を退けました。この戦いで柴田勝家は手傷を負っています。
柴田勢を蹴散らした信長勢は、次に林美作勢へ向かい、信長自身が槍で美作を突き伏せ、首を取りました。信勝は戦いに出てきていませんが、信長は自ら最前線に立ち、暴れまくっています。信長の700弱という手勢は、いつものように信長に忠誠を誓った親衛隊でしょう。
数は少なくとも戦闘専用集団ゆえ、士気は高く強かったようです。暴れまくる信長に従って、3倍近い敵を蹴散らし、討ち取った首は450以上もあったのでした。合戦は稲生町2-12の伊奴神社あたりの広域であったようです。その死者を弔う庚申塚(西区庄内通4-30)では古戦場跡として今も地元で供養祭が催されています。ぜひ現地へ行ってみてください。