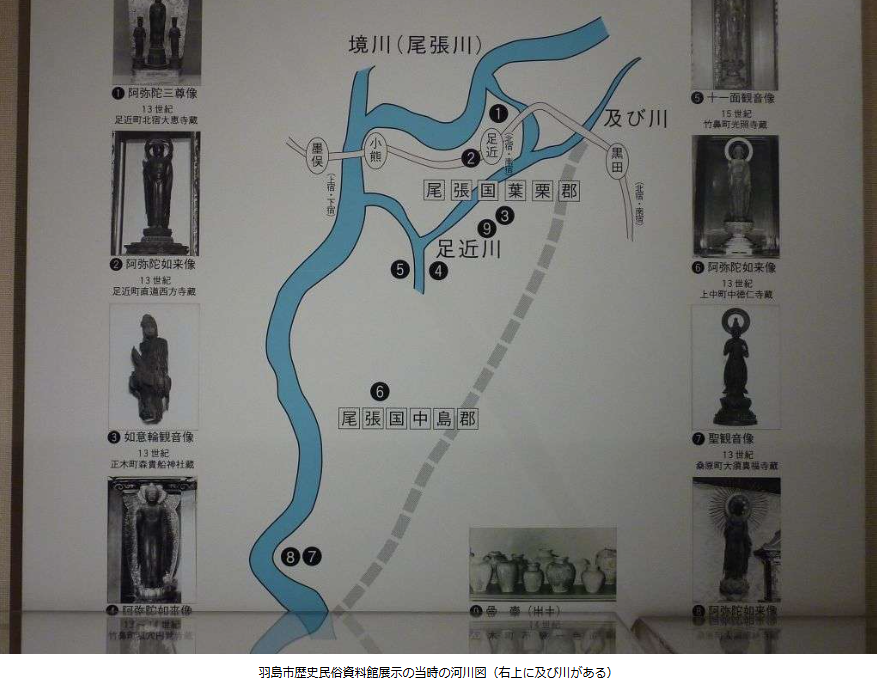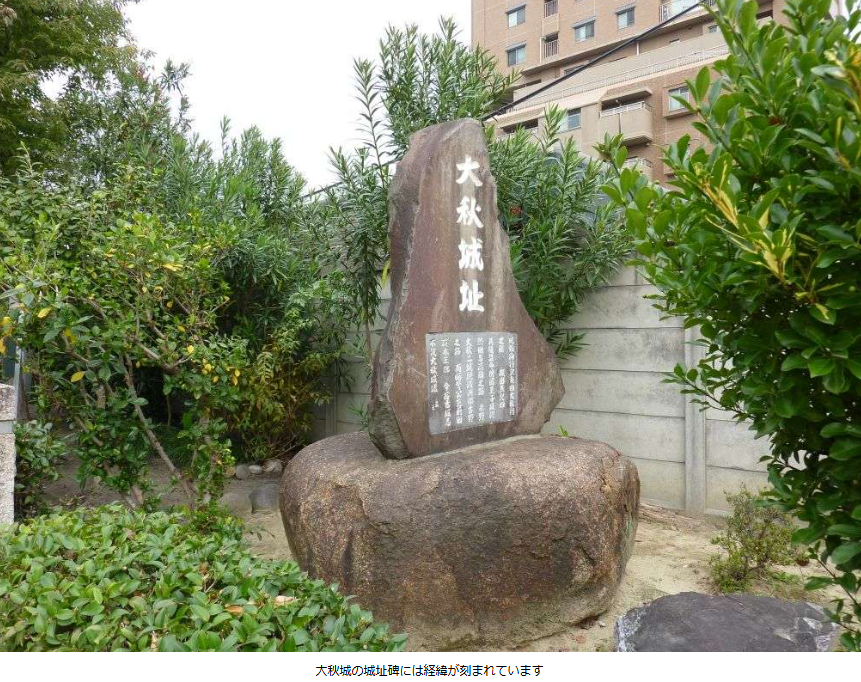2013年3月15日
1556年の4月に斎藤道三の弔い合戦に破れて清須へ戻ってきた満22歳の信長ですが、道三の後ろ盾がなくなったことで、いよいよ家臣の中からも、さらには織田一族からも反信長の機運が高まってきます。
まずは尾張上四郡を支配するとされる岩倉の織田伊勢守家が、道三を殺して意気上がる美濃の斎藤龍興と組んだようです。そして信長へ小競り合いを仕掛けてきます。国道22号線に下之郷という交差点(清須市春日中沼66)がありますが、このあたりにあった下之郷村は、当時信長方でした。そこを岩倉勢が襲ったので、信長はやり返しました。

そのうち今度は稲沢市の下津(おりつ)にあった正眼寺(現在は小牧市にありますが、当時は五条川沿いにあり、信長方の砦だったようです)を3000の兵で襲ってきました。信長も出陣しましたが、動員できたのはわずか83騎のみで、しかたなく百姓衆に竹槍を持たせて後方を守らせ、足軽戦を行ったと言います。それでもこの時点ではなんとか岩倉勢を追い払っています。
この頃、信長は家中全体を掌握しきっていませんでした。中でも同じ母親の弟、信勝(一般には信行という名で知られています)は、破天荒な信長と違って真面目で有能とされ、古くからの家臣団の間では人気が高く、また母親(信長の実母でもある土田殿)も信長ではなく信勝を支持していました。父の葬儀に遊び着のまま来て、抹香を投げつけて帰るような信長を、父の時代からの家臣団はいまだに受け入れ難かったようです。
またはっきりしていませんが、信長を支えた叔父信光が、清州城を乗っ取って信長に渡した途端に殺された(信長が暗殺した?)ことも家臣団がまとまらない要因のようです。また信長が重視するのは自らが鍛えている親衛隊の名も無き若者達ばかり、というあたりに不満があったのかもしれません。
このまま信長の下にいてはいずれ滅んでqしまう、そんな危機感が家臣の中にはありました。そこで信長を廃して信勝を立て、織田信安や斎藤義龍と和睦したほうがいいのではないかと家臣らは考え始めたのでした。
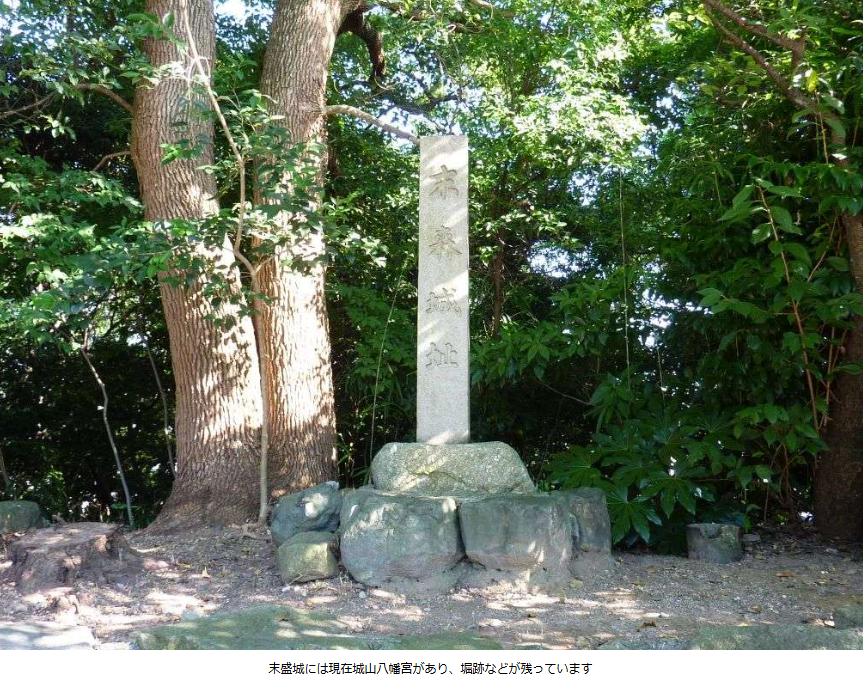
信勝は母とともに父信秀が作った末盛城(千種区城山町2-88)に居ました。信長への謀反を企む信長の筆頭家老林秀貞は那古野城(中区)に、有力武将の柴田勝家は下社城(名東区陸前町1310)に、そして守山城(守山区)では信長の信頼厚かった城主信時が家臣から殺され、さらには岩崎(日進市)の丹羽氏勝も反信長の旗色を鮮明にしつつありました。
道三の死からわずか一ヶ月で、庄内川の東側(愛智郡)はほぼ反信長となったのでした。そしていよいよ稲生の戦いが勃発します。それは次回に。