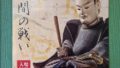2023年11月25日

大河ドラマ「どうする家康」もいよいよ最終盤ですが、11月19日放送分では榊原康政(杉野遥亮)と本多忠勝(山田裕貴)が老いた姿を晒していました。若い役者二人の老け役はかなり無理があるなあと微笑ましく観ておりましたが、その榊原康政が生まれたとされるのが三河の上野。今は豊田市上郷町で、東名高速上郷サービスエリアの南、愛知環状鉄道三河上郷駅近くに上野城址がありますがここが康政誕生地となっています。康政の活躍に関しては私の研究の守備範囲ではないので書きませんけど、12月2日土曜日開催の鳴海中日文化センターの講座で、この城跡を現地訪問する予定です。というのもこの城は、榊原康政より以前、信長の時代にはかなり重要な場所だったからです。

上野城は応仁の乱のころ、尾張富田にいた戸田宗光がここに移って築いた城とされています。戸田氏はその後渥美半島に移り、信長の時代には田原や今橋(豊橋)などで侵攻してくる今川勢と戦っています。上野城は戸田氏の後、阿部氏が入り、北部の金谷城中条氏、寺部城鱸(すずき)氏、伊保城三宅氏、八草城那須氏らと組んで安城松平氏と戦ったという話もありますが、このあたり、本当のところはどうにもよくわかりません。ただ重要なのはこの上野から北部(現在の豊田市界隈)は、上記のように一体感のある地域で、信長の時代には高橋郡とも呼ばれました(上野は高橋郡に入るか微妙な位置ですが)。今でもそうですが、三河でも岡崎・安城あたりとはちょっと異なる地域です。

榊原康政は天文17年(1548年)に上野城で生まれたとされますが、上野城は榊原氏の城ではないので実際は違うでしょう。城跡には誕生碑がありますが、そこから南に300mほどの集落にもう一つ古い誕生碑があります。こちらには上野下村城があったとされますが、おそらくこちらの集落こそ康政の生まれたところでしょう。上野城の方にはそのころ酒井忠尚(ただよし)が入っていました。この人は大河ドラマで大森南朋が演じた酒井忠次の叔父とか本家(つまり兄)とかいわれていますが、はっきりしません。かつては信長父の信秀と組んでいましたが、今川氏の三河制圧により今川義元に下りました。しかし、天文24年には反今川の狼煙を上げ、今川方の大村綱次と戦っています。ところが翌年には銭三百三十貫文で買収され寝返ります。こう書くと優柔不断な人に見えますが、それだけ実力があって、どちらも欲した人物・地域だったということでしょう。後の一向一揆では反家康側となり、一揆終結後も抵抗を続けて敗北。行方知れずになりました。康政は松平に反抗したこういう忠尚をどう見ていたでしょうか。

さて、上野から北、豊田市中心部あたりがいわゆる高橋郡です。かつては高橋荘という荘園で、信長の時代には佐久間氏の領地となって尾張高橋郡となりました。しかし江戸時代にはこの郡名は消えています。通説では永禄3年5月の桶狭間の戦いのあと、翌4年4月に信長がこのエリアへ兵を出したとされています。しかしその頃にはもう家康と同盟しているので、出兵する意味などないはず。これはおかしい。このころ信長は美濃侵攻を進めており、三河方面を安定させるために家康と組んだのですから、どうも納得できません。通説の根拠は『信長公記』の首巻に、「翌年4月上旬,三州梅が坪の城へ御手遣……野陣を懸けさせられ,是より高橋郡御働き」と書かれていることから。桶狭間合戦の記事のあとに何年とは書かずにこの高橋郡出兵記事が置かれているので、翌年、つまり永禄4年とされているわけです。しかし首巻の記事は厳密に年代別に並べてあるわけではないので、疑問が深まるわけです。
信長が攻めたのは『信長公記』によれば金谷村、梅坪城、伊保城、八草城です。そこで今回、鳴海中日文化センターの2023年後期講座では、この上野城から北部の高橋郡をいろいろ考え、現地へも行くことにしました。先月はまず金谷城へ行きました。ここは南北朝時代には中条氏の城でした。中条氏は足利三代将軍義満の頃には三河の北部で強大な力を持っていましたが、信長の時代にはすでに没落していて、金谷城も無人だったようです(信長公記には城攻めではなく町に火をつけたと書かれているため)。豊田市金谷町の集落の勝手神社に城址碑が在りますが、実はその東側の台地(現在は畠と竹林)が城址だったようです。行けば城らしい立地と見事な堀を見られます。近所には信長に焼かれたという伝承を持つ三光寺もありました。

信長は梅ケ坪城を攻撃した。しかし城主が誰なのか、わかりません。それどころか梅ケ坪城は位置さえわからないのです。通説では名鉄梅ケ坪駅のあたりとされていますが、全くの平地で、おそらくそこではないでしょう。その西の山にある霊岩寺が城址ではないかといわれていますが、立地としては申し分ないのになぜか全く伝承がありません。信長が攻めたという有名な城なのになぜ?

更に信長は愛知環状鉄道沿いに北へ進み、伊保の城を攻めます。ここは保見団地のあたり。近世に立派な城が築かれているため分かりづらいですが、信長の時代の城はおそらく保見東古城か西古城でしょう。これもどちらなんでしょうか。そして誰がいた城なのでしょうか。

さらにもう一箇所攻めたのが八草城。こちらはリニアの八草駅の南ですが、愛知環状鉄道が城跡を破壊しているとのことで何もないかと思いましたが、行ってみたら本丸と思しき平地がちゃんと乗っていました。ここを攻めてから信長はたぶん、現在のモリコロパークの中を通って尾張へ帰っています。

さて信長が攻めていない高橋郡の城が矢作川の東にある寺部城です。桶狭間の戦いの前年には信長側だったこの城の鈴木氏を助けるために、信長が周りの城を攻めたと考えるとすっきりするのですが、確証はありません。この城は1558年に家康側が攻めたとされ、家康の初陣の地とされていますが、この時家康は17歳で、ちょっと初陣には遅すぎ。寺部の戦いは勝利したので初陣にでっちあげられただけで、実際にはその2年前、大敗北を期した「日近の戦い」が初陣ではないかと言う説もあります。ちなみにこの寺部城は、どうする家康にも登場した渡辺守綱が尾張藩家老として江戸時代初期に入った城です。ここには守綱寺(しゅこうじ)や家老の屋敷(の塀)が現存するなど、守綱に関連する見どころもいろいろ在ります。


そして家康に攻められた寺部城を助けたとされるのが矢作川上流の東広瀬城三宅氏。ここには織田方の佐久間氏が入っていたという西広瀬城もあるのですが、それはいったいいつの話?など、まあ高橋郡は謎ばかり。ということで、信長はいつ高橋郡を攻めたのかを検討してみようというのが今回の講座ですが、マニアックすぎて参加者がいつもより少ないので、ぜひご参加いただけるとありがたいです。12月2日は上野城、伊保城、八草城へ行く予定。1月、2月は寒いので室内講座として、3月になったら東広瀬城へも出かける予定です。よろしければぜひご参加を。お問い合わせは0120-538-7639へ