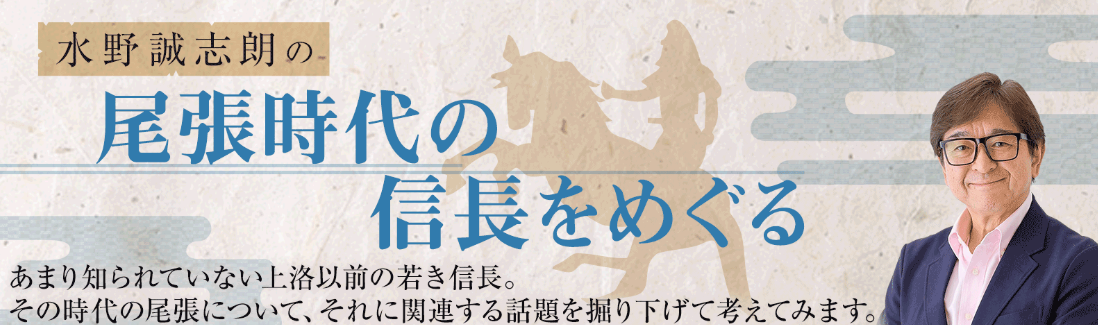中日新聞のwebサイト『達人に訊け』が閉鎖となりましたので、2012年9月4日から連載を始めた信長記事を、こちらで再録します。
10年以上前の記事ゆえ、現在の研究と齟齬があることもありますので、訂正を加えている事を御了承ください。
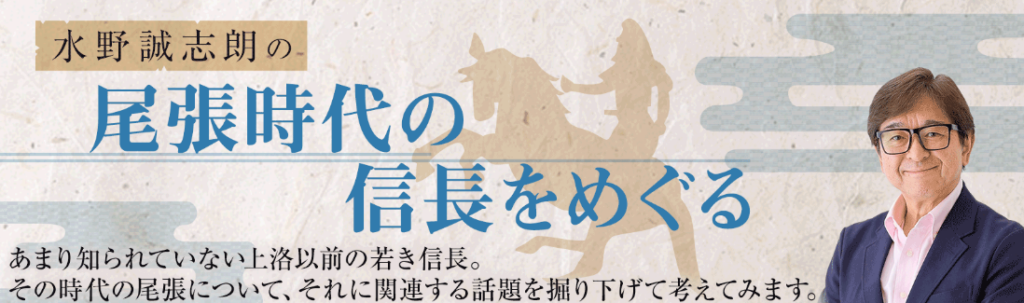
2012年9月4日
最近は自分史を書くのがちょっとしたブームになってますが、戦国時代の有名な武将は自分の生きた証を残したでしょうか。
実はほとんどそれらしい資料は残っていないようです。自伝という概念もなかった時代ですし、何より、戦いに敗れて滅ぼされてしまえば、たとえ記録があったとしても勝者側が焼き尽くしてしまったでしょう。そんな中で、織田信長はしっかりとした伝記『信長公記(しんちょうこうき)』が残っています。
といっても信長が自分でそんなものを書くわけはなく、書いたのは当時の家臣であった太田牛一(おおたうしかず)という人。信長より7歳年長だった牛一は今の名古屋市北区のあたり、尾張国山田郡山田庄安食村の生まれで、信長の家臣として戦いの前線に立ってきた人でした。
牛一は弓の名手として信長に褒美をもらっているほどの武人ですが、若いころから記録好きだったようで、岐阜城へ入るまでの信長の若き日を、『信長公記』とよばれる一代記の別編「首巻」として後世に残しました。本能寺で信長は殺されましたが、やがて部下の秀吉が、その後は同盟していた家康が天下を取ったこともあって、この貴重な記録は消されず残ったのです。
この「首巻」を読むと、若き信長が残した足跡が尾張各地にたくさんあることに驚かされます。そしてそれらはあまり知られていません。例えば信長が生まれたのは勝幡城であったという説が最近の主流ですが、その勝幡城跡も今から10年ほど前にやっと認知され、地元中心に盛り上がってきたほどです。

この連載ではこうした信長ゆかりの地へ思い立ったらすぐ出かけられるようにご紹介していきますので、気楽にお付き合いください。
※2012年の頃は太田牛一を「おおたぎゅういち」と呼ぶのが普通だったが、2024年現在では「おおたうしかつ」と呼ぶようになってきた。子孫が一の字をかずと読んでいるためで、「うしかず」あるいは「うしかつ」と呼ぶのが正しいと考えられるようになってきている。