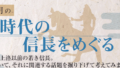2012年9月14日
信長は1534年(天文3年)に生まれたとされています。では生まれたのはどこでしょうか。それを知るにはまず信長の父、織田信秀を知ることが必要です。
織田信秀という人は尾張下四郡(しもよんぐん=愛智郡、智多郡、海東郡、海西郡)の守護代であった織田達勝、この人に付いた三奉行の一人、という地位とされてきました。当時は、守護、守護代、奉行ということになり、三番目の地位とされますが、それは尾張の半分のエリアにすぎません。しかし信秀には才覚があり、武力と経済力、そして人望でやがて尾張に散らばる織田一族の筆頭にのし上がっていきました。
信秀は津島神社に近い海東郡勝幡に城を構えていましたが、津島神社のある津島は当時、一大水運貿易都市で、信秀はここを支配しており、津島の湊が生み出す経済力が彼の権力を支えました。この時代もやはりお金がなければ武力や政治力を持つことはできなかったわけです。当時信秀は、伊勢神宮、さらには天皇家にまで大金を寄付しています。
信秀は信長が満4歳の時に今川那古野氏の氏豊が居た那古野城を略取し、やがてここを信長に与えました。那古野城は今の名古屋城の二の丸庭園あたりにあったとされる古城です。そして信秀自身は古渡に新しい城を作って移りました。地下鉄上前津駅近くの真宗大谷派東別院のある場所がそこで、東別院の敷地内に古渡城の碑が建っています。
こうしたことから信長が生まれたのは、昔から言われてきた那古野城ではなく、信長が生まれた頃、父信秀が住んでいた勝幡城ではないか、という説が近年有力です。
それよりここで不思議なのは、今川義元の弟とも言われる今川氏豊が那古野城にいた事実です。つまりその頃、那古野城のあたりまで今川が勢力を伸ばしていたことになります。尾張のどれくらいが当時、今川領だったのでしょうか? このあたりはまだはっきりしたことがわからないようです。今川義元が桶狭間まで来たのは、領土回復という意図があったのかもしれません。
ともあれ、まずは勝幡城址へ行ってみましょう。カーナビかスマホに「愛知県稲沢市平和町城之内93」と入れて向かってください。このあたりは三宅川と日光川の合流地点で、川を堀に使えば強固な城ができそうです。また当時の川は物流路でもあり、三宅川は上って行くと稲沢の国府宮につながっています。
勝幡城址は現在空き地となっており、碑が一本建っているだけで遺構はありませんが、西側のよめふり橋に行くと、勝幡城復元図が欄干に表示されていますので、往時を偲べます。
さて、ここまで来たのなら信秀やそれをついだ信長の経済拠点、津島まで足を伸ばしましょう。クルマなら15分ほどです。当時も馬ならそんなものでしょう。カーナビには「津島市本町1-52-1」あるいは「0567-25-2701」と入力してください。

そこは津島市観光交流センター「まつりの館 津島屋」で、津島の歴史や観光名所がひと通りわかります。津島屋を起点に歩いて市内観光に出るといいでしょう。
津島といえば有名な津島天王祭ですが、津島屋には信長も見たであろう祭り風景の屏風絵もあります。信長は天王橋という橋の上からこの祭りを見たそうですが、その橋の跡地も残っています。現在は埋め立てられて池となっていますが、当時の天王橋は約130メートルの長さの大橋だったそうです。伊勢湾に近く、大きな川が流れていて、水運が盛んだった勝幡と津島、ここが信長ルーツの地です。