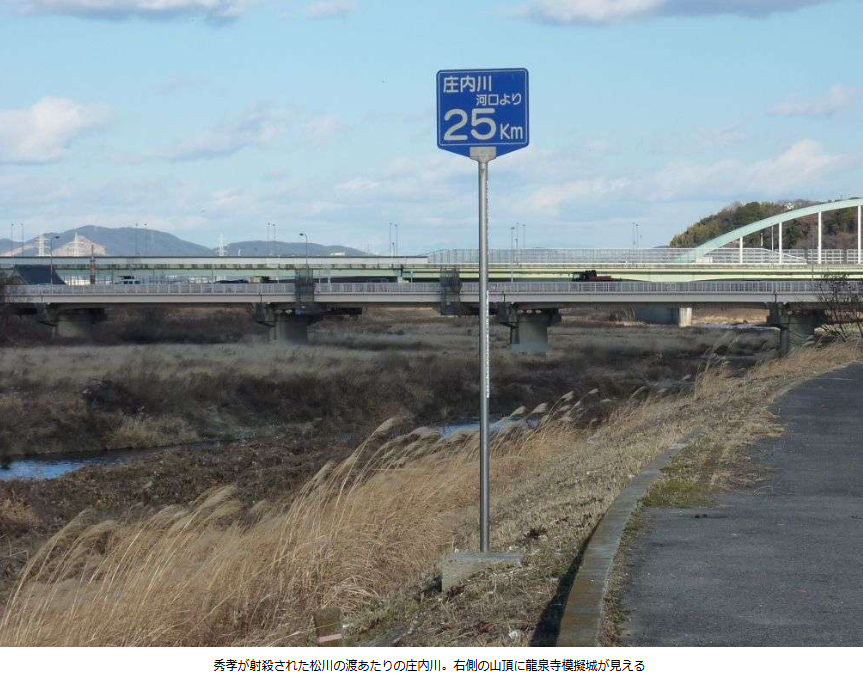2013年2月1日
1554年4月についに清須城に入った信長ですが、尾張の支配は、まだほとんどといっていいほどできてはいません。整理してみますと、尾張八郡の内、広い上四郡は岩倉の織田大和守家が引き続き抑えています。(※この見方は近年見直しが進んでいる。このころの尾張には山田郡も存在していた)
下四郡のうち那古野城のある愛智郡は、叔父の信光のものになってしまい、その内でも鳴海や大高、笠寺のあたりはすでに今川方の手に落ちていました。また知多郡は独立系の水野氏など、地元武将が力を持っていました。
この時点で信長は、生まれた勝幡や津島のある海東郡、海西郡といった下四郡の小さなエリアを支配しているに過ぎず、その海東郡も弥富・鯏浦(うぐいら)島の一向衆である服部左京進らが信長に従おうとはしませんでした。それでも蟹江は信長の支配下にあったようです。(※支配していたかに関しては疑問が残る。あくまで信長方であったということだろう)

そんな信長の実力を試すかのように、1555年8月になると服部左京進の手引きによって、三河武士を中心とした今川勢が海路上陸して、蟹江城(城址は海部郡蟹江町蟹江本町城)を攻めました。(※この戦いの有り無し、またその実相はよくわかっていない)
この頃は今の国道1号線あたりが伊勢湾の海岸線ですので、弥富も蟹江も海岸に接していました。はっきりしたことはわかりませんが、想像するにこの軍勢は大高・鳴海方面から出撃したのではないでしょうか。この時蟹江城は落城したとされています。今も信長街道という道が残っているほど、蟹江は信長にとって地元でした。信長、相当なピンチです。

そしてピンチは更に続きます。翌1556年11月22日には信頼する美濃の義理父斎藤道三が、嫡男義龍にその座を奪われ、城を追われました。新たに美濃の主となった義龍が、尾張上四郡の織田大和守家と手を組めば、信長はひとたまりもありません。この大ピンチに信長はどうしたのでしょうか。